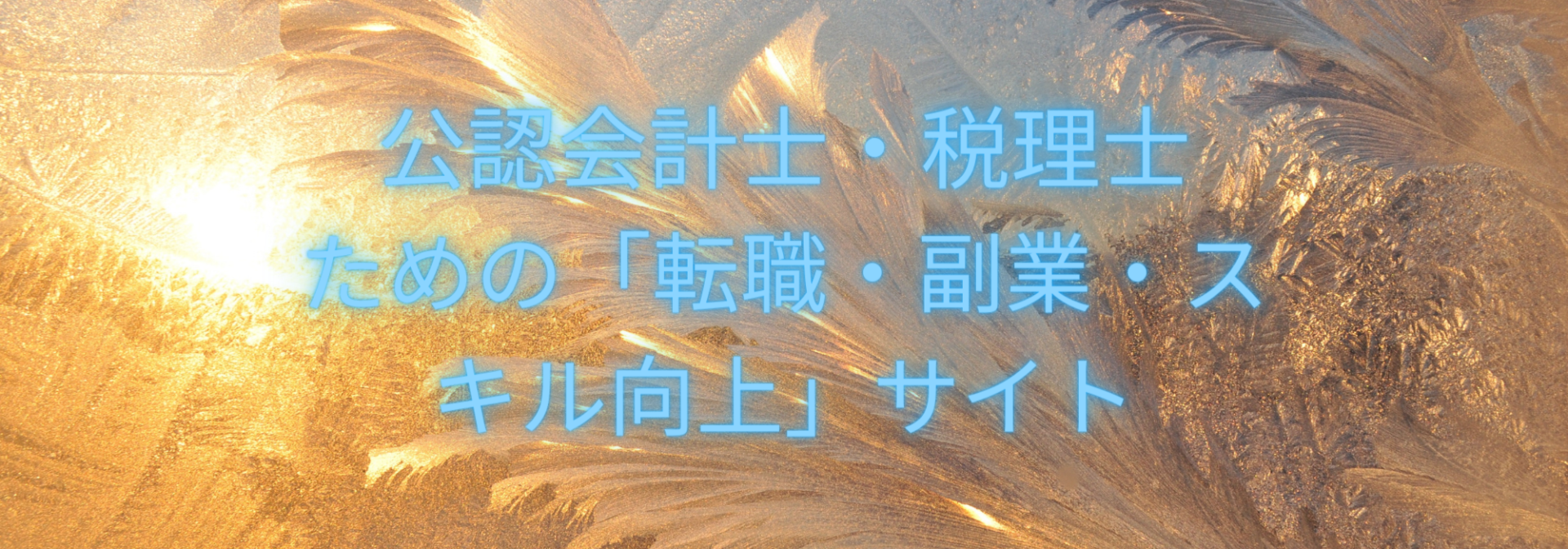当記事では、「監査法人の仕事についていけないな。、」と感じる方に向けて、その対応策について記載したいと思います。

公認会計士のKENと申します。
監査法人やIPO支援機関、FAS系税理士法人で計8年ほど仕事したのち、独立しています。
今でこそ、要領よく仕事をこなせるようになりましたが、
(昔の自分のように)今一つ、器用に仕事をこなせない人向けにアドバイスができればと思います。
耳が痛いと感じる方もいるかもしれませんが、是非参考にしていただければ幸いです。
それでは、監査法人の仕事についていけない原因ですが、主に以下の四つが挙げられるように感じます。
- お客さんから感謝されないから、モチベーションがあがらない。(その結果業務の進捗に徐々に支障をきたす。)
- 気づかぬうちに、必要以上に知識のインプットする一方、業務へのアウトプットが足りない。
- 監査チーム内の人間関係をうまく構築できていない。
- 同期や優秀な先輩と比較して、同じレベルの仕事ができない、と自分を卑下してしまう。
簡潔に言えば、
- やりがい
- 時間対効果が悪い
- コミュニケーションの問題
- 自己肯定感
こういった部分かと思います。
※マイナビのプロモーションを含みます。
お客さんから感謝されないから、モチベーションがあがらない。(結果業務進捗に徐々に、支障をきたす。)
監査業務は抽象度の高い仕事です。
どういうことかというと、仕事・サービスとしての付加価値が見えづらく、やりがいが見出しづらいです。
受験時代の最初に学んだように、監査は「投資家の意思決定情報として機能するように」とありますが、
経理部も優秀な方であればあるほど、ビジネスの実態を適切に現す経理作業を行いますし、
その適正性について監査人からの「保証」を求めます。
監査ではなく、例えば税務、コンサルティングの仕事をしていると、
例えば、利益1億会社(法人税等が3,000万としたとき)でキャッシュアウト(節税)を200万円こちらのアドバイスで成功できたら、それは社長や経理部からとても喜ばれます。
これが付加価値が見えやすい(抽象度の低い)仕事です。
一方、監査の仕事は、経理部の人たちの利益に直接貢献するものと言い難い側面があります。
必要であれば、資料の作成をこちらから要求する場合もありますし、追加の資料提出を要求する場面もあります。(経理部からすれば面倒です。)
そして、投資家から直接感謝されることは少ないですし、「保証を付与すること」で初めて仕事を完結したことになります。
また、その保証とは、
投資家が求めている保証の水準とは、実質的に不正の防止です。
「時間・資源的制約があるから、不正調査までの機能は背負えない」という監査の理屈はあまり、通らないといっていいでしょう。
とすれば、
この問題に対する対応策
監査法人に所属する人は、真面目な方が多く、「お客さんのために・・」という意識が強い人が多くいらっしゃいます。
私も仕事する以上は、お客さんに喜ばれる仕事ができればな、と一生懸命監査業務に携わりました。
ただ、事実として、上記に記したような、期待ギャップがあり、思ったような「やりがい」を感じづらく、
そのため、そういう性質の仕事だと事実は知っておく必要があります。
その一方、



「監査法人は、お金をもらえる大学院」なんていわれることがありますね。
総会議事録や取締役会議事録、上場企業の内部統制に係るあらゆる資料を見て、リアルなビジネスの現場を見、知ることができます。
これらの業務からどれだけ生の勉強ができるかが、吸収できるかが、監査法人での仕事を楽しくするコツなのかと感じます。
中小企業の税務顧問の仕事をしていて、時々感じます。
「この会社のビジネス規模がスケールし、上場企業レベルになった際」どのように内部統制を敷くかなど。
もっと監査法人在籍時代に、勉強・吸収できることがあったのではないかと感じます。
是非、監査先クライアントが行なっているビジネスから様々なことを理解して、やりがい、モチベーションを感じる意識をもってください。
同期や優秀な先輩と比較してしまい、パフォーマンスを落とす。
監査法人には、優秀な同期や先輩が多くいらっしゃいます。
ともすれば、その方々と比較をすることで、自己否定してしまうこともあるでしょう。
私もそういうことがありました。
ただ、技術面、能力面で差があることは当たり前ですし、上をみればキリがありません。
自分が「今」できるMaxのパフォーマンスをその瞬間瞬間でどれだけできるかが、職業会計人としての成長につながりますし、
ゆくゆく力になります。(比較するのは、「他人」ではなく「過去の自分」です。)
転職という手立てについて
といっても実際のところ、他の人と一緒に仕事をしていると、比較はしてしまうものです。
監査法人は出世競争がないといわれつつも実際、マネージャー、パートナーへの年次が近くなるにつれ、
出世競争は存在しますね。
そんな時に他の人と比較するな、という方が難しいです。
ただあなたは公認会計士の活躍の場がたくさんあることは認識していますか?
このように言葉で書き記す以上に、公認会計士の活躍フィールドというのは、数多くあります。
監査法人だけではありません。
税務、 FAS、金融、コンサルティング・・
また企業内部に入り込み、経理、経営企画、内部監査室、はたまたIPO・・
ここでは、会計士が転職する場合についての、活躍する場についてみていきます。
公認会計士の転職市場と「キー」となる転職エージェント
上記にざっと公認会計士が携わることができる業務について掲げましたが、
あなたは上記のうち、どれだけそれら業務内容の説明ができますか?
イメージがついていますでしょうか?
例えば、FAS業務の中のM&Aバリュエーション。
なんとなくテキストで学んだ株主価値の評価額計算を思い浮かべますが、
実際のところ仕事の本質はそこにありません。
株のbuyerとsellerがいて、両者の双方が価格で売買が行われるよう、計算式を理屈づけすること仕事の基礎になります。
その一環に、デューデリジェンスも含まれます。
ただ、こういった仕事、実務に対する基礎理解は、実務を通して学ぶこと外ないことがほとんどでしょう。
ただ、実務の入り口を知る手段はあります。
それは転職エージェントに出されている求人を40件、50件と眺めることです。
転職エージェントの優位性
今では、会計に関わる業務を行っている会社は転職エージェント、もしくは転職サイトを活用しています。
そして、転職エージェントにだされている求人票はいわば、「企業の広告等、PR」でもあります。
丁寧に業務内容について書かれている会社からは、その企業がどんな事業で利益を出しているか、
また自分がどんな業務に携わることができるか、丁寧に書かれています。
全ての企業がそうであるわけではありませんが、
求人票、そしてさらにそこから企業HPとふかぼりしていくと、
転職先のイメージがとてもつかみやすくなります。
また転職エージェントは転職サイトと違い、その企業について事業内容の質問をすることもできます。
転職エージェント担当者も人間ですので、
転職活動、また情報収集に積極的な人には、どんどん前のめりでサポートしてくださいますし、
これを無料で利用できるメリットはかなり大きいです。
ぜひ、積極的に利用しましょう。
おすすめの転職エージェント
この項の最後におすすめの転職エージェントについてお伝えします。
現在の市場では、公認会計士向けと言いながらも求人数を幅広く取り揃えていなかったり、
業界が偏っていたり、と転職エージェントによって特色があることが多いです。
複数社登録を検討されている方であれば、
バランスのとれた大手の総合型(リクルートやDODAなど)と、会計専門職特化型の2パターンについて、
登録することもお勧めしますが、
まずは、公認会計士向け総合型として求人数4,000件以上保有している
マイナビ会計士
公式サイト:
※マイナビのプロモーションを含みます。
マイナビ会計士では、大手マイナビ社の高いブランド力と信頼性をベースに、
他エージェントを凌ぐ圧倒的求人数4,000件以上を保有していています。
Ms-japanや、ジャスネットキャリア、rexアドバイザーズなど、公認会計士向けの転職エージェントはありますが、
どこの転職エージェントも1000件前後の求人数しか保有していないのが現状です。
その点、マイナビ会計士はその4倍もの求人数を保有しています。
業界研究や情報収集するには、まず要登録の転職エージェントといえるでしょう。
もう一点、特筆すべきはカウンセラーの誠実性です。



私は複数回、マイナビ会計士を利用して転職していますが、カウンセラーの皆さん、とても懇切丁寧にカウンセリングしてくださいます^^
実際に転職までは考えていなくても、(情報収集目的であっても)
嫌な顔せず、丁寧に対応してくださるのはとても助かります。
是非、マイナビ会計士で情報収集の第一歩目をふんでみてください。
事項からは、監査法人の仕事についていけない3つ目の理由についてみていきます。
監査チーム内の人間関係をうまく構築できていない。
コミュニケーションの問題は、すぐに解決することは難しいです。
ただ、一つポイントとして挙げられることとして、人間関係構築能力、コミュニケーション能力というのも、監査の技術と同様に、一つのスキルです。
このことを知っているか知らないかだけでも、大きな差があります。



コミュニケーションの改善は難しい・・!



コミュニケーションは試行錯誤の繰り返しで改善できる!!
このことは「自己肯定感」とも関連しますが、
私は、このいった人間の心、マインドの原理をスクールで教わりました。
下記のスクールです。


【公式】コミュトレ|全く新しい実践形式のビジネススクール
上長とのコミュニケーションに悩んだ時期があり、いくつかコミュニケーションのスクールを検討した中から通学を決めたスクールです。
同じようにコミュニケーションに悩みや不安を抱えているビジネスマン(それも商社マンやコンサルの方など)素晴らしい経歴をもった方もたくさん通学していました。
スクールでは、話す上で基本となる聴く姿勢や、表情の取り方など、簡単なことから一つずつ、実践に次ぐ実践で少しずつスキルアップできるように講座が作られています。



監査チーム内でのコミュニケーションで活用できるかな??
最初は、不安でしたが、監査チーム内どころか、プライベート・恋愛にも応用ができ、自分の中にあるコミュニケーションに対するハードル(難しさ)を下げることができました。
費用も安くありませんし、コミュニケーションの学校だから、無理な営業をさせられる心配もありましたが、全くの杞憂で、
講師の方も同じようにコミュニケーションに苦手意識を持っていた人が講師になっているケースもあります。
ですので、それ特有の悩みというのが、スクール内でナレッジとして蓄積されています。(空気が読めない、相手の心を引き出せない etc.)
無料体験会も実施しているので、是非お話し聴いてみてください。
コミュトレの公式HPはこちら(気づかぬうちに)必要以上の知識のインプットする一方、アウトプットに活きていない。(時間対効果が悪い)
監査調書の作成には、クライアントのビジネスの理解、会計基準・監査基準の理解、またそれらの知識のアップデートが必要になります。
試験勉強時の大量のインプットする習慣が身についていると、仕事を始めてもこの習慣から抜け出せず、必要以上の知識をインプットしてしまうことに陥ることがあります。
漫然と会計基準、監査基準の読み込みなどを行っていると、気付かぬうちに、多くの時間をインプットに費やしてしまいます。
転職という選択肢について:
「仕事についていけない」と感じているからと言って
転職するという判断は、悪いわけではありませんが、ベストな選択肢ではないことも往々にしていありますね。
あまり前向きな転職理由ではありませんし、当然のことながら転職活動中、企業やファームによってはその後ろ向き具合をよしとしないところは多くあります。
しかしながら、そんな曖昧な、後ろ向きな転職理由でも、比較的うまくいってしまうのが会計士の転職市場でもあります。
会計士が伸び伸び活躍できる転職先は本当に数多く、市場のニーズは多く、あなたが知らないだけ、というケースが数多くあります。
ワークライフバランスがとれ、監査法人のような出世競争がない(ハイパフォーマンスをそこまで求められない)転職先も多くあります。
少しずつ情報収集、市場調査からでも始めてみてはいかがでしょうか。
本日も最後まで読んでくださりありがとうございます。